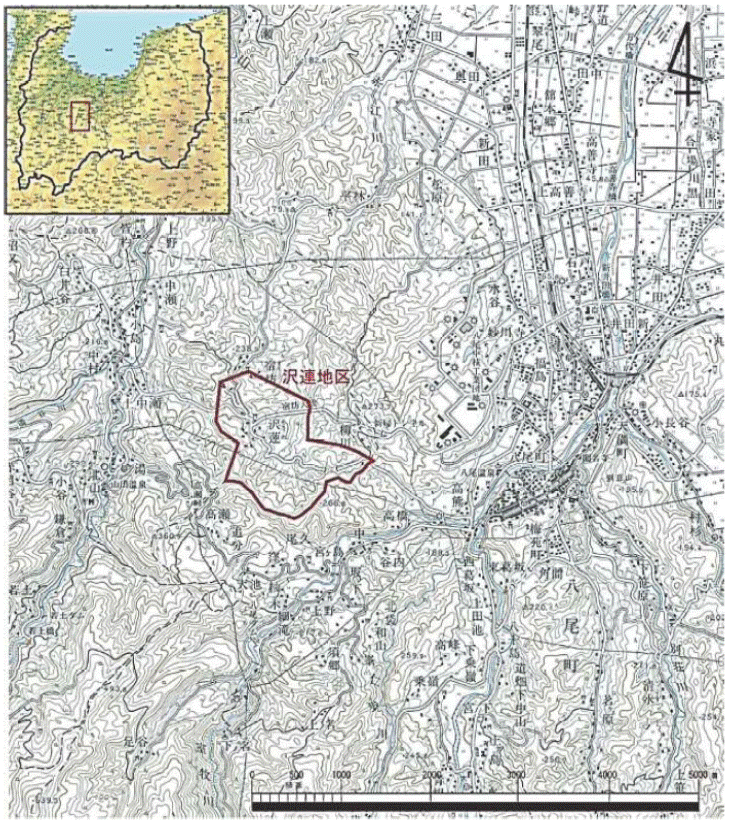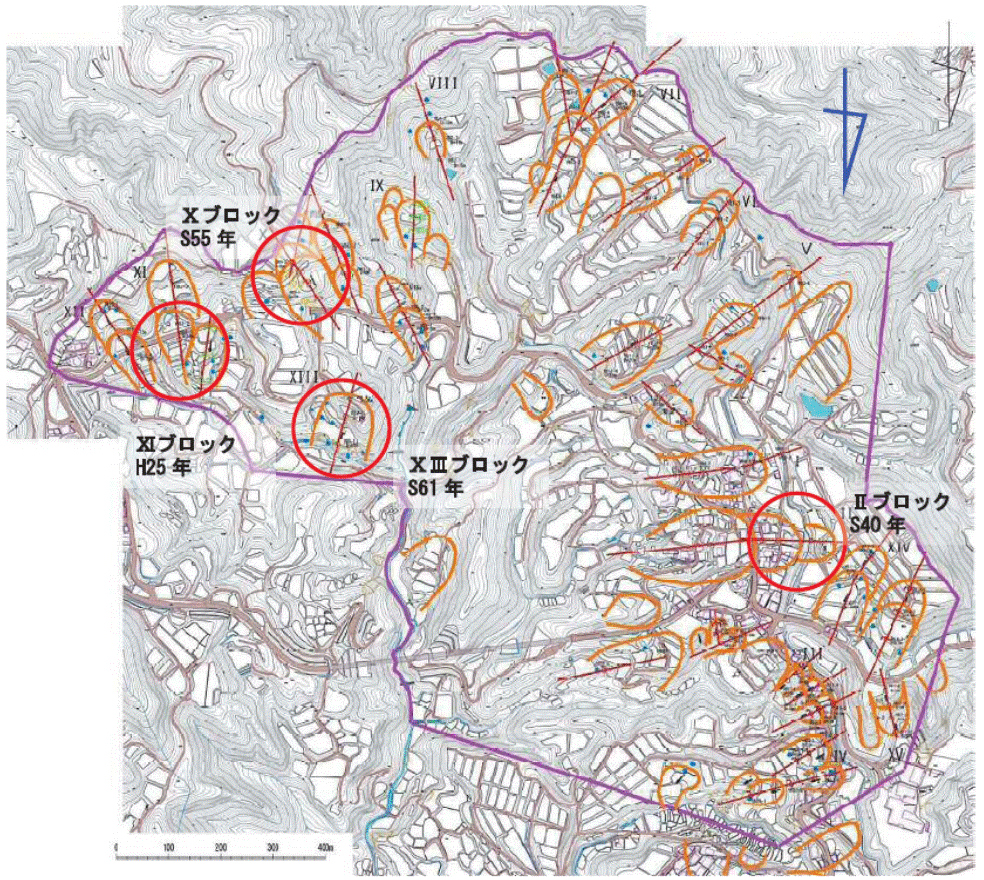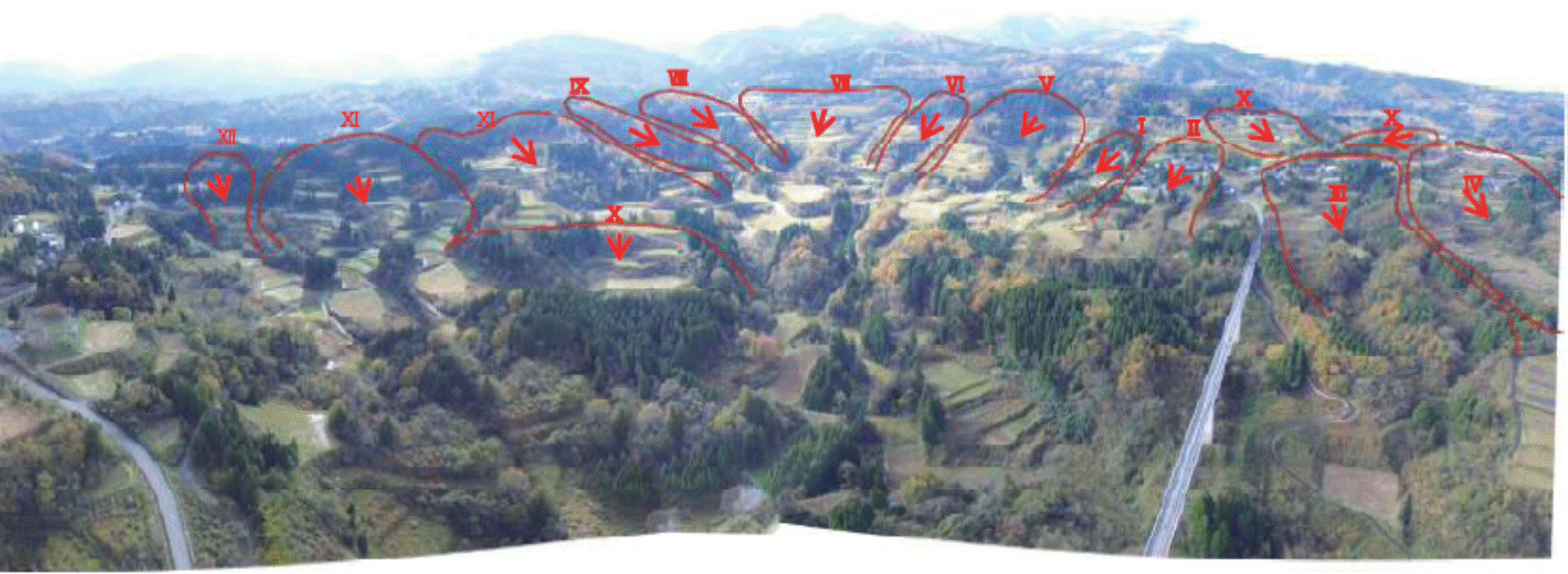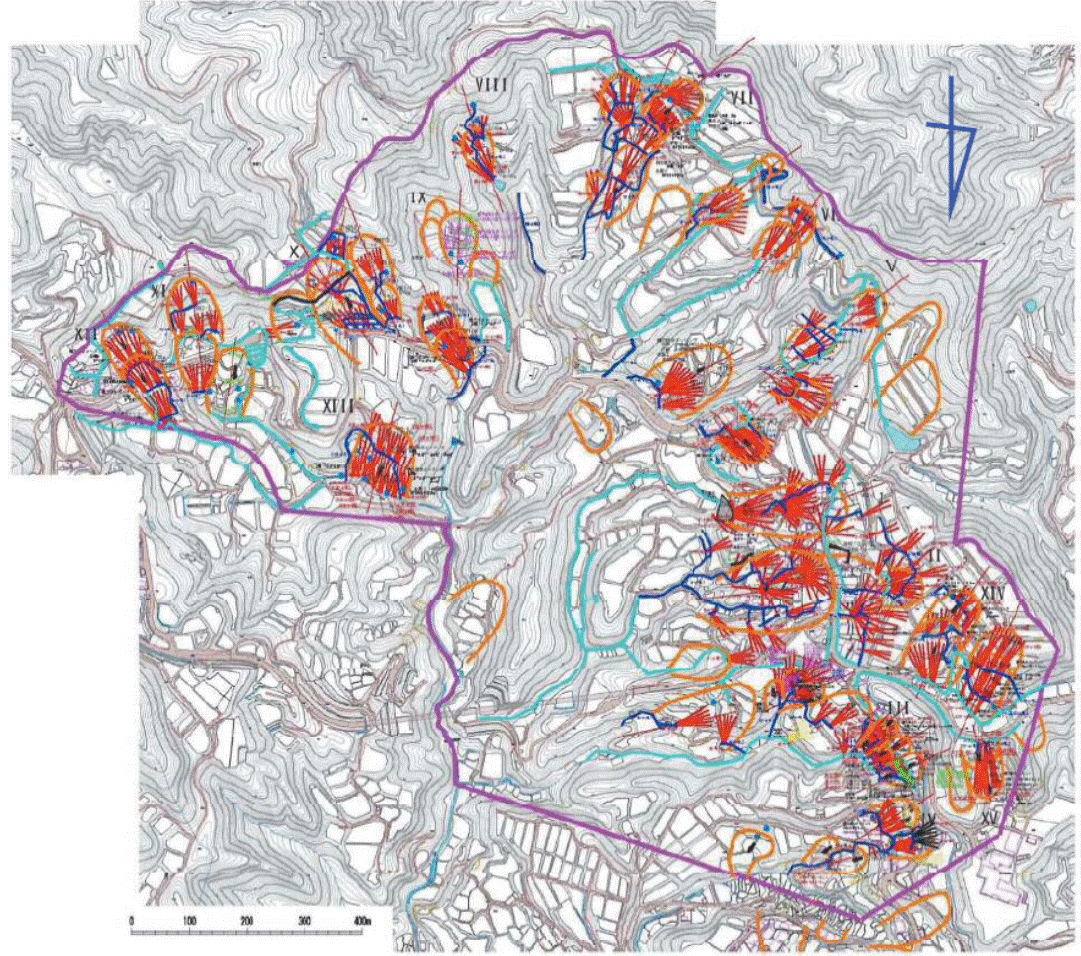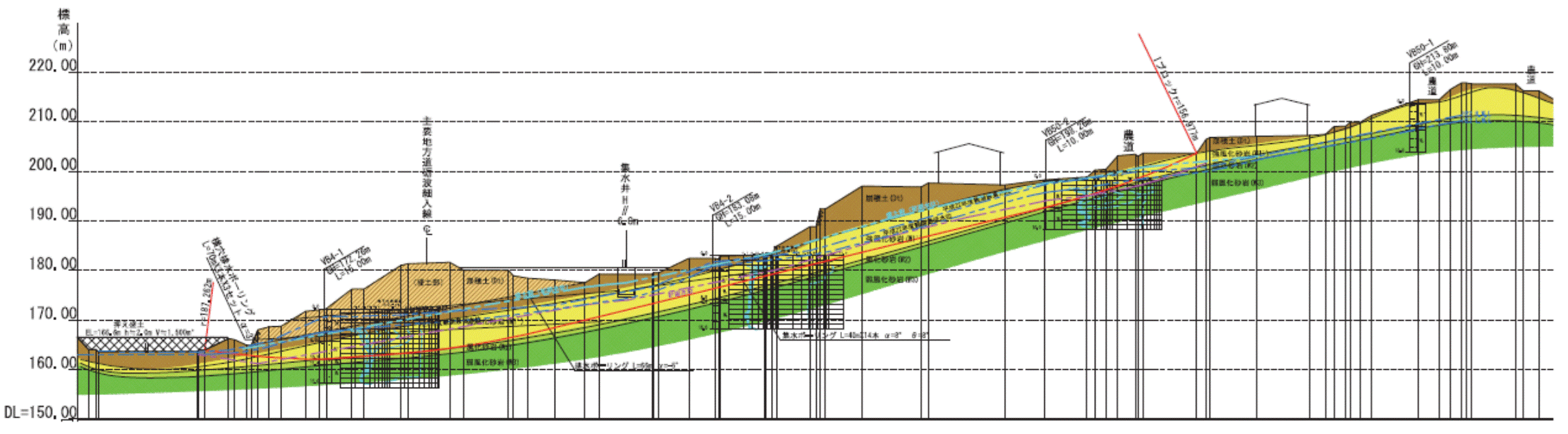沢連地区地すべり
国土交通省所管
富山県
地すべりの概要
1.地すべりの概要
沢連地区地すべりは、JR高山線越中八尾駅の西方約3kmの中山間地にあり、北側の一部は宿坊地内、また東側の一部は柳川地内にかかっている。地区のほぼ中央には、延長470m、高き43mと大きな宿坊大橋が架かっている。
当地区は、昭和37年に地すべり防止区域に指定され、その後、昭和48年、昭和58年に追加指定された。現在の地すべり防止区域面積は143.6haとなっている。
近年では人命にかかわるような災害は発生していないが、地すべり性の変動が繰り返し発生している。
2.地形・地質概要
- 地形
- 沢連地区は、赤江川の源流域にあたり、赤江川を取り囲むようにして北(赤江川の流下方向)へ開かれた緩やかなすりばち状の地形を呈している。地すべりは、この谷の先端から階段状に連なるように多く発生している。
- 地質
- 沢連地区に分布する地質は、砂岩・泥岩を主体とする新第三紀の堆積岩(北陸層群八尾累層に対比される、聞名寺砂岩・泥岩互層)を主体とする地層で、一部では泥岩主体の地層(城山泥岩層に相当)が分布する。
3.地すべり状況
沢連地区地すべりは、Ⅰ~ⅩⅢブロックの14ブロックに区分される(ⅩⅠブロックは2ブロック)。
- 昭和40年:Ⅱブロックで、地すべりが発生。
- 昭和55年:Ⅹブロックで、10月の集中豪雨時に県道を寸断する様に幅120m、長さ210mの規模で、地すべりが発生。
- 昭和61年:ⅩⅢブロックで、春の融雪期に、幅30mの崩壊性地すべりが発生。
- 平成25年:ⅩⅠブロックで、台風通過に伴う豪雨によって、ブロック内を横断する県道の盛土斜面で崩壊が発生した他、夏季の停滞前線による連続降雨により小規模な崩壊が発生。
4.地すべり機構
- 素因
- ① 地質が新第三紀の堆積岩であり、風化すると脆弱化しやすいこと
- 誘因
- ① 降雨、融雪による地下水位の上昇
② 斜面末端の赤江川の侵食による斜面不安定化
5.対策工
- 対象ブロック:14ブロック
-
- 横ボーリング工:208セット(ΣL=33,535m)
- 集水井工:7基
- グラウンドアンカー工